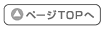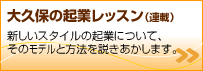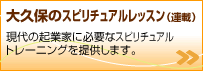緩和ケアの診療所、在宅ホスピス医

がん患者は、病院で痛みに耐えながら亡くなる例が多いです。25年前、日本の医療現場に問題意識をもった内藤いづみさんは、在宅ホスピス医として「最期は自宅で」と望む人の「さようなら」と「ありがとう」がひとつになる生と死を支えています。
起業したとき
仕事の経験 |
結婚 | 子ども |
|---|---|---|
| 生かした | していた | いた |
プロフィール
念願の医大に入学したものの組織になじめず、また先端医療優先主義の日本の医療現場に疑問を感じる。ある患者との交流から在宅ホスピス医に興味を持ち、イギリスへ留学。帰国後、日本の病院にも勤務するが、ひとりひとりの患者に向き合う自分らしい医療がしたいと、1995年起業。ふじ内科クリニックを開業し、在宅ホスピス医に。書籍の執筆やマスメディア出演、講演なども多数で、幸せで自分らしい豊かな生き方と死の迎え方を多くの人に伝えている。
起業年表
| 年齢 | 西暦 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 24歳 | 1981年 |
福島県立医科大学卒業。三井記念病院・内科で研修医として勤務 |
| 26歳 | 1983年 | 東京女子医大・第一内科に勤務。イギリス人と結婚 |
| 29歳 | 1986年 | 夫と共にイギリスに移住し、ホスピスにて非常勤医として研修を受ける |
| 34歳 | 1991年 | 日本に帰国し、湯村温泉病院に勤務。 |
| 38歳 | 1995年 | ふじ内科クリニックを開業 |
| 40歳 | 1997年 | 『ホスピス 最期の輝きのために』、『あした野原に出てみよう−在宅ホスピス医のノートから』(いずれもオフィスエム発行)を出版 |
| 41歳 | 1998年 | 第6回日本ホスピス・在宅ケア研究会、全国大会会長を務める |
| 49歳 | 2006年 | 山梨県青少年協会の理事長を務め、7月からは甲府家庭裁判所委員を務める |
起業ストーリー
その人らしい豊かな生命の最期に寄り添う
「どんな最期を迎えたい?」。そう聞かれたら、どう皆さんは応えるでしょうか。病院のベッドで激しい痛みに耐えながら亡くなることを望む人は、そう多くないはず。しかし、最新治療を持ってしても治療が困難な末期がん患者は、自分ががんだとも知らされず、延命のためにたくさんの管につながれ、病院のベッドで痛みと孤独に耐えながら最期を迎えるケースも……。内藤いづみさんは、日本の医療現場への疑問を25年ほど前に感じ、現在は山梨県甲府市を拠点に在宅ホスピス医として活動を続けています。「目の前に患者さんという、ぬくもりのあるひとりの人間がいるのに、症状だけを診て、その人の存在、人生を見ていないというか……。医療の現場に情がない。大学は最先端医療の研究ばかりで、人間の命や心の問題を語り合う場も仲間もなかったですし、これが私の志してきた医療なんだろうかと。内科医として大学病院に勤務しても、当時、疑問は増すばかりでした」。
そんな時、あるひとりの患者に出会いました。彼女はがんが転移した23歳の女性。化学療法の繰り返しで髪は抜け落ち、激しい痛みと闘いながら衰弱し、無数の管につながられた身動きできない状態のまま最期を迎えることが予想されました。「どうしたい?」、その女性に内藤さんは聞きます。「家で家族と過ごしたい」。内藤さんは毎日往診することを約束し、彼女の望みをかなえます。マッサージがいいと聞けば、その専門家のところまで同行。生の望みと死という現実との間で、内藤さんは彼女に寄り添います。それから4ヶ月後、若い命は母親の腕の中で逝きました。「うそをつかず、真実を本人、家族と共有しながら、一緒に最期まで歩むということを、彼女から教わりました。彼女に出会って別れを経験して、進むべき道が決まりました」。また、作家の遠藤周作(故人)さんとの交流も、内藤さんが在宅ホスピス医への進む後押しになりました。週刊誌で遠藤さんが「心温かな病院がほしい」と書いている記事を読んで、医療の現場で見聞きし、感じてきた思いをつづった手紙を遠藤さんに投函。以来、それに感銘を受けた遠藤さんご夫妻との交流が続いたのでした。
ホスピスの本場イギリスで、目指していた医療に出合う
転機は1986年、イギリス人の夫の転勤によって訪れます。夫は石油会社の日本支社に勤務していましたが、本社へ戻ることになったのです。イギリスといえば、ホスピスの本場。内藤さんは家族と共に渡英し、ホスピスで非常勤講師として活動し始めました。「ホスピスというと、病院内にある施設をイメージする人が多いと思いますが、そもそもは『ホスピタリティ(温かくもてなす)』を語源にしたもの。患者さんの心と体の痛みを取り除き、本人だけでなく家族も支える活動や哲学を表す言葉なのです。イギリスに行って共鳴したのは、しっかりした施設を用意するでもなく、ホームドクターと熟練したナース、そして地域ボランティアが支える、街で支えるホスピスだったということでした。患者は往診で痛みを取り除いてもらいながら、自分がしたい日常を最期まで送る。私が目指していたものはこれだと思いました」。
1991年、内藤さんの志に賛同した夫は転職し、家族で帰国。内藤さんが中・高校時代を過ごした山梨県甲府市に居住。市内の病院に勤務しながら、有志と「山梨ホスピス研究会」を発足しましたが、「元来、組織は苦手なタイプなんです」と内藤さん。自分の哲学を通すなら、組織に属さず、自分でやるに限ると1995年、ふじ内科クリニックを開業しました。「自由な立場でいたいと、医師会にも入りませんでしたから、目立ったことはしないようにと、看板も見えないような場所にそっと立てたりして。とはいっても、ラジオ出演や講演なども多くて、けっこう大胆な発言や活動もしていましたがね」と笑う。そんな噂を聞きつけ、内藤さんを頼る人が口コミで少しずつ増えていきました。「でも、経営は火の車でした。患者さんの話を聞くのに、1時間近く診察することもありますし、余分な薬は出しませんので、診療点数も低い。私はほぼ無給。スタッフや看護師にも十分な給料を出せませんでした」。午前中は外来を受けながら、電話相談も受け、午後はがん患者の自宅へと往診。夜は急変などで入る患者からの連絡に応対するために、枕元には携帯電話とバッグを起き、すぐ飛び出して行けるようジャージを着て眠る毎日でした。
人生を生き切るための医療を伝え続けていきたい
そんな内藤さんを嫉妬やモルヒネに対する世間的な偏見からか「ドクター・デス」などと陰口を叩く人もいました。しかし、自分なりの哲学を持って患者と向き合っている内藤さんは、そんな声も一笑に付します。「いくら医療が進歩しても、死の予防はできない。誰にでも訪れるものです。この世を去ることに未練を感じた時、人は得難い人生の輝きに気づきます。そこからが新しい生の始まり。その輝く時をどう生き、どう終わらせるか。そのサポートこそ、私がすべき仕事だから。医療チームと家族、患者本人で力を合わせ、その人らしい臨終を迎えた時、決して死は医療にとっての敗北ではありません」。開業から3年経った1998年には、クリニックを移転。それまではビルの2階を拠点にしてきましたが、末期がん患者の中には階段の昇り降りが苦しい人もいます。それを考慮して、1階でバリアフリー設計のクリニックへと移転したのでした。「場所を移すというのは、新たな気持ちに切り変わるもの。最初は目立ちすぎないように、と考えていましたが、もっともっとホスピスを日本に広めるためにも、自分を看板にして、堂々とやろうと。移転を機に、覚悟が定まったと思っています」。
ホスピスをもっと日本に根付かせたい――。内藤さんはそのために、在宅ホスピス医として活動する一方、マスメディアへの登場や講演活動も積極的です。著書も多数出版していきました。2009年春には絵本や講和集も発行する予定です。「事業を広げていくつもりはありません。深めていきたい。だから、伝えることは惜しみなく行っていくつもりです。人間として学ぶべき究極は『ホスピタリティとコミュニケーション』じゃないかと思うのです。どの仕事分野の人でも、この力を養えば充実して生きていけるはず。でも医療の世界では圧倒的に欠けています。だから、自分ももっと養っていきたいし、医療に携わる人たちに伝えていきたいとも思っています」。内藤さんは、人生を最期まで生き切ることを勧める医師「ライフ・ドクター」といえるのではないでしょうか。
会社概要
| 会社(団体)名 | ふじ内科クリニック |
|---|---|
| URL | http://www.naito-izumi.net/ |
| 創業 | 1995年4月 |
| 業務内容 | 在宅ホスピス、内科外来 |
(内藤 いづみさんの場合)
起業のきっかけ、動機

病状だけを診て、その人の存在、人生を見ていない医療現場にずっと違和感を感じながらも、内科の医師として病院に勤めていた時、ある末期がんの女性患者に出会いました。「家に帰りたい」という女性の言葉から、在宅で最期を迎えることを支える在宅ホスピス医に関心を寄せるようになりました。イギリスでホスピス医として経験を積み、帰国後、日本の病院に務めながら、講演活動などを始めたのですが、自分の哲学を貫き、ひとりひとりの患者と向き合うには、自分で病院を開業するしかないと独立しました。
起業までに準備したこと
物件を借りて設備を整えることです。物件は、自宅と子どもが通う幼稚園の間というアクセスの良い場所で見つけました。設備に関しては、イギリスの在宅ホスピスは簡素なオフィスのような感じだったので、それでもいいかと最初は思ったのですが、内科の外来も受け付けるにはある程度、医療設備も必要だと考え、最小限の整備をしました。壁は夫がペンキで塗ってくれたりと手づくりしました。
起業時に一番苦労したこと
看護師は、働きたいと言ってくれるスタッフがたくさんいたのですが、幼い子どもの面倒を見てもらうためのベビーシッターと、医療事務を担当してくれる事務員はなかなか見つからず、焦りました。本業である医療に関する知識はあっても、経理などの知識がなかったため、医療事務員は必須。幸い直前になって、人からの紹介で適任者が見つかりましたが、当時はかなり焦りました。
だからうまく起業できた!…その一番の理由

人に恵まれたことでしょうか。起業当時は、自分の哲学をどれだけ貫くか、力を発揮するかばかりにどうしてもとらわれがちです。自分が気づかない基本的なことをスタッフや周囲の方から教えてもらうことが多く、たくさんの勉強をさせてもらいました。
起業時の環境(友人や家族の協力他)
夫はクリニックの壁を塗ってくれたり、配線をしてくれたりと協力的でしたし、家族は何といっても心の支えになってくれました。また、東京女子医大に勤務している当時に手紙を出して以来、交流が続いていた作家の故・遠藤周作先生や、ラジオ・講演などでご一緒した永六輔さん、尊敬する医師の鎌田實先生も支えになりました。
最初のお客さんと営業方法
自由な医療がしたいと医師会に所属せず開業したので、ビル2階で看板も見えないくらいひっそりと始めました。しかし、以前に勤務していた病院の患者さんや、私が出演したラジオなどを聞いて探していらっしゃる方など口コミで少しずつ増えていきました。
起業の際の重要ポイント
借金を抱えないで始めたことが、自分のやりたいことを貫く結果になったと思います。借金をして事業を大きく始めたことで、返済しなくてはいけない焦りもあるのか、自分のやりたいピュアなところから離れていってしまった知り合いもいます。私の場合は、事業を広げることではなく、ひとりひとりの患者さんとの関わりを深めていくことが目標だったので、大きなクリニックは必要ないと思っていましたし、実際に最低限の設備で小さく始めることから始めました。
役に立った情報源や相談先
故・遠藤周作先生や永六輔さん、鎌田實先生は、人生の先輩として素晴らしい相談相手でした。また、医療関係者の知り合いなど、多くの方にアドバイスをいただきました。
開業資金
医院開設には専門家に内装やマーケティングを依頼したりする人も多いので、通常、1000万円以上はかかるものと言われていますが、私は内装も手づくりで、最小限の設備で始めたので400万円くらいです。貯蓄を使いました。一番多く割いたのが、スタッフの人件費と運転資金で、私はずいぶんの間、ほぼ無報酬で働いていました。それもあって周囲からは「日本で一番貧乏な医者」なんて笑われていました。
活動拠点(事務所・店など)
最初は自宅と子どもが通う幼稚園とのちょうど真ん中に位置する、ビルの2階にクリニックを開業しました。しかし、末期がんの患者さんには2階への階段の昇り降りが苦しい人もいますので、3年後に現在の場所に移転。1階でバリアフリー設計にしました。
起業時の管理体制の整備(税理士、弁護士、弁理士など)
初年度の日常の会計は経理事務が行い、決算に関しては自分で行いました。翌年からは会計士にお願いしています。社会保険労務士へは問題が出てきた時に依頼しています。弁護士は特にまだ依頼するようなトラブルにはなっていませんが、備えとして紹介してもらっています。
起業後の転機

クリニックをビルの2階から、現在の1階の場所に移転した時でしょうか。開業当初は自分の名前を看板に掲げることに躊躇していた部分もあったのですが、クリニック開設から3年、書籍を出版したり、マスメディアに出ることも増え、そしていざ移転という時は、事業を仕切り直すようなものでした。自分を看板に掲げて堂々とやっていこうという強さというか、覚悟が持てました。
起業して自分が成長したと感じたこと
患者さんひとりひとりにスタッフと一緒に向かい合い、命の最期まで寄り添った時です。人間から人間についてのことを学ばせていただいたと、いつもいつも成長を感じます。
起業を志す人への一言アドバイス
やりたいことがあるけれど、今は何らかの事情ですぐにはできないとしても、できるチャンスが訪れた時には、そのチャンスを見逃さず飛び込んでいくことです。ただ、現状がイヤだから今の仕事を辞めたい、というのが起業の動機だと続けるのは難しいでしょう。心の中にどうしてもやりたいと思うことがあるなら、それは起業して苦しい時があったとしても続けられるはず。自分の心に問うてみるといいでしょう。
気分転換のしかた
音楽とダンスが大好きなので、月に1回は上京して、ミュージカルなどを観賞するようにしています。一度、患者さんを前に、過労のためか声が出なくなって体が固まってしまったことがありました。その時は知恵の総動員で、鍼灸の先生にカウンセラー、主治医に適切な指示をもらってどうにか乗り越えましたが、その時、体調管理と息抜きの大切さを思い知りました。
その他伝えたいことなど
私は起業する際、自宅と子どもが通う幼稚園の真ん中にクリニックを開設することで、アクセスしやすい状況をつくりましたが、子育てをしながら事業をする人は、こういったアイデアが大事だと思います。また、子育ては、仕事に突っ走る自分にブレーキをかけて守ってくれるものでもあります。ですから、子育てしながら事業を始めると、子育てが終わった途端に仕事に夢中になって無茶をしがちになります。体調管理には気をつけることが大事です。

業種別では、自分が興味のあるテーマで、年代別では、 自分と共通の年代(起業時)で、また地域別では自分に近い地域で、どのように起業されたのかなどがわかります。
また何が障害になりそうかなどをチェックしてみましょう。
必要になるのかを確認してみましょう。
- 初めての方へ
- 起業講座(e ラーニング)
- 女性起業家情報
- 業種別事例集
- 年代別事例集
- 20代
- 30代
- 人生設計を手伝うファイナンシャル・プランナー
- コミュニティレストラン&デイサービスの運営
- 山形の伝統を残す漬物の製造販売
- 働く独身女性のためのシェアハウス
- ハウスクリーニング・家事代行業・整理収納
- 緩和ケアの診療所、在宅ホスピス医
- 人事制度改革アドバイス・マーケティング事業
- 天草の自然海塩の製造・卸し・販売
- オーガニックに特化した飲料メーカー
- 家族向け日帰り温泉
- スリング、育児用品の製造・販売
- ラム酒の製造・販売
- イーコマースに関するコンサルティング・支援事業
- 授乳服の製造・販売
- タイと日本の国際交流ビジネスを目指す
- シックハウスを作らない設計事務所を目指す
- ITを駆使して、幅広くビジネス展開
- 医療子育て相談・代替医療
- 親子のためのスキンケア商品の開発・製造・販売
- 足と靴のカウンセリング・インソール製造販売
- 言語障害・発達障害の子どもと親のサポート
- 子どもの金銭教育
- 働き続けたいという要望に応えるネットオフィス
- お母さんを応援したい・ベビーシッター会社
- 女性の身体をケアするための複合施設
- ハウスクリーニング事業のパイオニア
- 美濃和紙で作るウエディングドレス
- 40代
- 50代
- 60代
- 地域別事例集
- 起業のポイントから
- 起業お役立ち事典
- 起業相談FAQ
- 関連リンク集
- アンケート
- 広告の掲載について
- わたしと起業comニューズレター
- 起業対談シリーズ